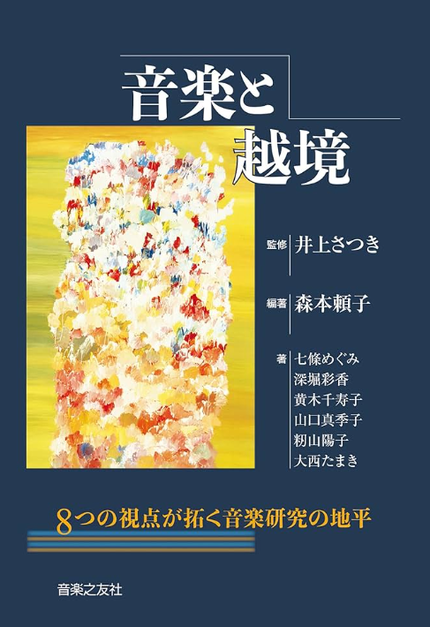
「音楽と越境 8つの視点が拓く音楽研究の地平」(井上さつき監修・森本頼子編著)を読んで。
【前置き】
日本の音楽研究者たちは、実際の演奏はさておき、音楽の何を研究しているのだろうか?
テーマの異なる8つの小論文。日本への最初の音楽伝来過程、ピアノ製造におけるヤマハの影の努力、戦国・江戸・明治時代の日本音楽マターと、世界情勢、侵略戦争と政治的圧力、そしてそこにおける音楽について各著者の研究がまとめられた書となっている。私なりに印象に残ったこと中心に、各章の主な内容をカテゴリ的に近いもので並べて簡単にサマリーしておく。
戦国・江戸・明治時代の日本音楽マター:日本への最初の音楽伝来過程、ピアノ製造におけるヤマハの影の努力
【第4章】日本には16世紀ザビエル渡来から禁教令までカトリック教会イエズス会による宣教とその影響によるキリスト教西洋音楽伝来の期間が存在する
- カトリックはその当時宗教改革によるプロテスタントとの分立の過程でカトリック刷新改革が試みられ聖歌も単旋律グレゴリオ聖歌への回帰へと向かった(時代の流れによって当時和声的な現代化の中にあった聖歌賛美が逆戻りへ)
- 彼ら(イエズス会)は当時日本人が初めて西洋音楽キリスト教音楽を受容する様子を記録し観察していた1500年代の中ごろのことである、初めは大きな違和感を持って見られたようだが特に子供たちが讃美歌を覚え歌を楽しみながらそのみ言や祈祷を無意識無自覚に覚え受け入れていったという
- 一方で当時の日本の音楽(音楽的文化)とイエズス会の持ってきた西洋音楽は全く異なっており双方にとって受け入れがたい苦痛に感じた者も多かった
- この16世紀に日本には琵琶法師が伝道師に転じてみ言を歌い伝えかつそれで生計を立てる例がイエズス会側の情報として報告されていたのは驚きである
- 宣教を目的として音楽を活用していく工夫がみられる(「積極的適応」と「消極的適応」)
- クラシック楽器の演奏法を教えることはせず歌の伴奏でのみ使用したり日本の当時の音楽的志向を取り入れたりして上手になじませるうちに感動して涙を流して喜ぶ市民がいたなどと詳細に報告されている(イエズス会からローマ教皇庁へ)
【第3章】ピアノの日本国内製造に関する関税問題についての歴史をたどる
- 1866年江戸幕府が外国製品の関税をたったの5%に設定
- 見直しが入るのが1899年明治このとき15%~40%へと(3倍~8倍)、ピアノ製造が進むが逆に関税率が高すぎて輸入に頼る製造用の部品の調達費が高くなりすぎて問題視される
- 1911-14年に改革、日露戦争・第一次世界大戦・関東大震災・第二次世界大戦などの有事や海外の為替変動など影響を及ぼす様々な要因があったことが述べられているし山葉が率先して適正な関税に関する要望を政権に提示していた事実があった、1937年の日中戦争まで日本のピアノ生産は右肩上がりであったが関税改革の影響で輸入が三割程度に抑えられヤマハが成長出来たという背景があった
音楽の背後の世界情勢:侵略と政治的圧力、そして音楽
【第1章】第一次大戦中の日本の音楽事情
- ベートーヴェン第九:1914年に勃発した日独戦でのドイツ人捕虜たちが1918年から5年間の休戦協定期間に日本初演したという(※第九は1824年に作曲される)
- ドイツ人捕虜たちによる90人規模ものオーケストラが頻繁に日々収容所で演奏していた、そして「音楽が」「彼らの健康に大きな役割を果たしている」「収容所の良好な環境を生み出し続けている」と本国へ報告されている
- 青島(19世紀末にドイツが占領した中国の港町):ここは第一次大戦で日本が20年程度の間にドイツ本国の音楽生活を彷彿とさせる民間と軍楽隊の管楽器主体のオーケストラで1シーズン16回ものポップからシリアス、交響曲からオペラまでベートーベンワーグナーまで。また批評が新聞でも大きく取り上げられるなど音楽が駐留するドイツ人だけではなく青島自体の生活と音楽
【第2章】日本への移民白系ロシア人?
- どうやら社会主義国家無神論ユートピア国家ビジョンに相容れないロシア人たちがいてロシア革命の1917年以降亡命する赤系ではない白系ロシア人が大量に出たと言う歴史が存在していたようだ。彼らがバレエ音楽芸術を日本を始めアジアに伝えてくれた。(こんな驚くような出来事情勢というのが歴史に秘められているんだな)
- 劇場専務取締役から破格のギャラで招請された89名からなる実力あるメンバーで帝国劇場公演が行われた(1919年)、カルメンやアイーダという有名オペラは全てロシア語翻訳版でこれが日本で初めての上演、入場料は通常の舞台の3倍だったがチケットは売り切れ行列、このように革命ロシアを亡命した芸術家たちと日本でのオペラ開眼の両者のニーズが合致して相乗効果を生んだというストーリー
【第5章】ポーランド人の苦難の歴史を忍ぶ力の源泉とは?
- ショパンは祖国を離れフランスに逃れた音楽家
- カトリックの信仰に根差した国民のアイデンティティ自覚だった
- スウェーデンの侵略やナチスの占領など悲劇に満ちたポーランドの作曲家たちも悲愴な曲を聖書に信仰に寄せて書いたということか
- そこには沈黙の神がおり自国の度重なる悲運に対し救いの手を差し伸べられない神への憤りさえ曲に投影せざるを得なかった悲しみが滲んでいるシマノフスキ、ペンデレツキ
【第6章】ソ連政権下で社会主義翼賛を無理強いされた作曲家たち音楽家たち
- 彼らも妥協か亡命かを迫られた精神的苦難を味わい続けてきた:ラフマニノフ、ホロビッツ(ウクライナ人ピアニスト)など
- ヘルマンシェルヘンという音楽家彼がシューベルトに見出した音楽の理想形はベートーヴェンのような押し付けがましい闘争的な劇場構成の音楽ではなく音響的で誰にでも歌えるそして共に歌わせるような自然な音楽でありロシア革命のときに人々が歓喜した開放の本当の実現を夢見る新しい音楽であったという
その他、【第7章】はメサイア作曲ヘンデルの英語詩への作曲について彼の姿勢と創造性に関して検証した論文、【第8章】はコロナパンデミックと音楽家たちが受けた試練、それを乗り越える試みについて、述べられていた。お金と地位ブランドのあるシカゴフィルはテレビ・ラジオ・ネットで過去の収録済コンテンツや演奏外のドキュメンタリーなどの付加コンテンツをメディア展開/ある楽団は外部とくに不特定多数の一般市民に参加を呼び掛けリモートアンサンブルをプロデュースして無料配信/またある楽団は市民に縁の深いロケーションで小編成の楽団が演奏する番組を展開/ある個人は自身の音楽家の知名度を武器に社会問題に対して発信しより大きな善のために貢献することに挑戦、といった例。
【一言感想】最も印象的だったのは結局「イエズス会による宣教とその影響によるキリスト教西洋音楽伝来」についての研究だった:かたやオペラやシンフォニーを操るヨーロッパのキリスト教文明と琵琶法師がわびしく寂しく唸る日本の文明がまさに伝道を接点に出会ったのであり、西洋楽器になど全くついていけない日本人には分かりやすい替え歌讃美歌で誤魔化して楽しませ浸透させた・・・それがイエズス会の作戦だった、という驚くべき事実。確かに言われてみればあったそうな歴史ではあろうが、考えてみたことも無かった。
