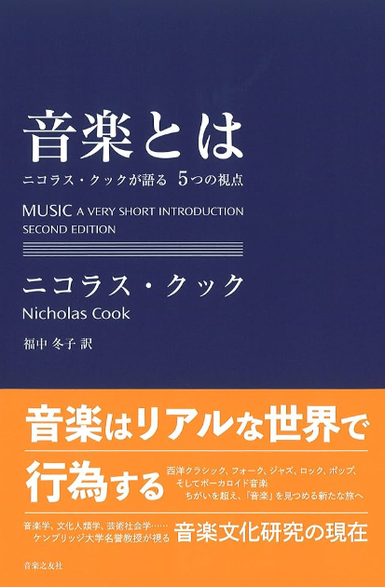
「音楽とは」(ニコラス・クック著)を読んで。
【前置き】まさにあらためて「音楽そのもの」について考える時間を与えてくれる、読み応えのある本。WAM(Western Art Musicいわゆる西洋音楽)偏重の音楽学に対する批判から入る著者が掘り下げている、「音楽を通じて人間性を回復する」という理念、「即興性を重視し台本のない生を生きる」という哲学、「音楽を社会的・文化的実践として捉える」視点、は私個人としてもとても共鳴するものだった。
音楽の社会的・文化的側面
【WAM(西洋芸術音楽)偏重への批判】
- 音楽学は全世界型・人類学的な行為という視点から再構築されるべき。
- 「西洋音楽」は寄せ集めであり、必然性ある伝統ではない。
【過去を持ち未来に向かって歩を進める文化、それが音楽】
- ワインや香水のように、音楽も体験であり、言語化は限界がある。
- 音楽は「文化実践と文化的制作物」の一つ。楽譜も、CDも、ダウンロードも、「あの曲いいよね」のその曲自体も、同じではないが全て音楽のカタチであり相互に関係しあっている。
【デジタル時代の音楽体験】
- 録音技術・個人デバイスの進化により、音楽体験は個人化。
- 「デジタル参画」によって共同体的音楽実践が復活。
- Spotifyなどのプラットフォームが感情と音楽の関係をデータ化。
即興性と人間の生の本質
【生は台本ではない:即興と創造性】
- 「老い」に向かって進む時間の中で「一瞬一瞬を懸命にかつ即興的に生きている」これが「人間」
- 英国の社会学者(エリザベス・ヘイラムとティム・インゴルド)は「人は、自身の生の時間が社会で共有される時間、つまり『種の空間』に生きている。人は自身の生を、行き先を描く地図のように考えがちだ。だが現実の生は異なる。つまり、あるいは未来を前に過去を振り返ることの出来る『種の空間』などは存在しないし、ただ一瞬一瞬を生きるのみだ。私たちは常に、未知の未来へと進むことで、即興と創造性は社会と文化の生の過程そのものに内在する。ヘイラムとインゴルドが言うに、即興的に反応する。」生は台本ではない。
【音楽における即興の重要性】
- 18世紀のクラシック音楽は即興演奏が基本。当時の音楽は(今では「クラシック」として楽譜の再現音楽として扱われるわけだが)当時の奏者たちには数字付低音や各奏者に即興的装飾音さらにソロのパートが与えられるなど即興演奏要素が基本的に求められていたのであり今日のよりジャズに近い。
- 現代のクラシック演奏は形式化されすぎており、指揮者が全てをコントロールしてしまうのは場合によっては官僚的・権威的にすら見える。音符通り弾く現代のクラシック奏者であっても実際のアンサンブルの時には互いの音を聞きながら様々なレベルで調整するPlayByEarを行っている。いずれにせよ音符通りに弾くという習慣がいかにつまらないものであり本来の音楽的行為から限定されたものかがわかる。
- ジャズのような「人種偏見のない平等な世界観」:(引用)1945年、アフリカ系アメリカ人の詩人でフォークロア研究者でもあるハーヴァード大教授のスターリング・ブラウンは、「ニグロも白人奏者も同じ人間として合流し、集団で即興し、自身が愛する音楽を創造し、演奏者の肌の色は問題とされない(オープンのセッション)」という名のもと実践される民主主義について語っている。
音楽とは何か:ニコラス・クックの視座「音楽は人間を取り戻す必要がある」
【音楽の普遍性と人間性の回復】
- 音楽は人生・幸福・アイデンティティを呼び覚ます力を持つ。
- デジタル化・社会変化の中でも、音楽の力は普遍的。
- 音楽は「人間を取り戻す」ための手段であり、「一瞬一瞬を懸命にかつ即興的に生きる」人間性を喚起する。
【音楽の両義性:善にも悪にもなりうる力】
- 音楽は政治に利用されることもあれば、政治を動かす力にもなる。
- 人種の壁を乗り越える希望にもなれば、差別を助長することもある。
- 音楽の力そのものは中立であり、善悪の責任は人間にある。「音楽の力とは善にも悪にも援用可能だし、まずもってそれは音楽の力に過ぎない。善悪の責任を担うのはあくまでも我々人間なのだから。」
音楽による壁の崩壊と共創
ダニエル・バレンボイムの多国籍アンサンブルは、音楽を通じて国境・文化・宗教の壁を越える試み。音楽が「共通の言語」として機能する可能性を示している。
【一言感想】音楽が人間に対しており、その理想の追求、人生、幸福、人間としてのアイデンティティを呼び覚ます存在として時代が変わりデジタル化する社会変化の中でも変わらず普遍的な力を持っているということを、コミカルな個人年金保険商品のテレビコマーシャルを取り上げながら、力説している。音楽は政治に利用されることもあれば政治を動かす力をも持ちうる、人種の壁を乗り越える希望にもなればかえって差別的意識を助長することにもなり得る「音楽の力とは善にも悪にも援用可能だし、まずもってそれは音楽の力に過ぎない。善悪の責任を担うのはあくまでも我々人間なのだから。」そして「音楽は人間を取り戻す必要がある」「一瞬一瞬を懸命にかつ即興的に生きている」これが「人間」、音楽によって人間性(人間らしさ人間の本来の姿)が喚起されるという事実に目を向けるべきである。
